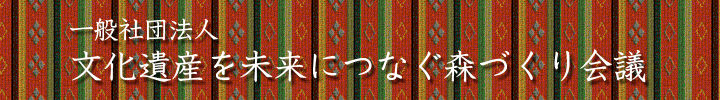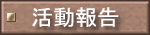秩父三峯研究集会報告
日時:平成15年3月8、9日
場所:三峯神社
秩父では前日30cmも雪が降り、山の上までの道路状況が心配された。だが翌日は、見事なまでの好天気に恵まれ、研究集会は開催された。周りの山々の雪景色と抜けるような青空に、感嘆の声しきり。パネルディスカッションや分科会の後も参加者同士の意見交換は、ここかしこで広がり、また深まって意義ある集会となった。以下はその報告である。
主催は、NPO法人木の建築フォラムと当会。共催に三峯神社。後援には、大滝村。協力、木の建築塾という陣容。挨拶、木の建築フォラム代表理事坂本巧氏、三峯神社宮司中山高嶺氏、大滝村村長山口民弥氏、当会からは伊藤延男氏が、趣旨と会への参加を呼びかけた。(以下敬称略)
パネルディスカッション
【秩父三峯神社の100年先を考える】
パネラーに・内山 節 当会代表、近藤光雄 当会理事、中山高嶺、野上 修、平野秀樹、渡辺 隆、進行役として植久哲男(住宅建築編集長)副で足本裕子当会事務局長が出演した。
以下、趣旨とディスカッションの抜粋を記す。
【中山高嶺 三峯神社宮司】
神社の周りの大きな木がもう600年経っている。そこに時々雷が落ちるので搬出するがご神木として売れるようだ。20年前に興雲閣をRC造であるが建てた。会場の報徳殿は、S39年大造営の時、その前の伊勢湾台風で被害を受けた倒木を使って建てた。無節のヒノキを使用、その時は、神社内に製材所があり、自前で行えた。また小教院という270年経つケヤキを使った建物は、平成2年1億をかけて復原したものである。昔の社務所も補強を入れて改修した。神社の修復には、国のお金が出るわけではないので、そういった補修費用の確保には、常に苦労している。
本殿や山門など、漆で塗られている。山の中にあるので湿気が多く漆が保存に向くが、前回 昭和39年に塗り替えてから、40年経ち平成16年完成予定で塗り替え工事中である。
【近藤光雄(財)文化財建造物保存技術協会 企画室長】
文化財の修理、用材の調達について、文化財には植物性資材が使用されていることが多いため、ある周期で修理を繰り返していく必要がある。近年、特にここ数年資材調達の問題が危惧されている。大径材にしても漆にしてもしかり、その中で特に顕著なのが、檜皮(ヒワダ)の問題である。檜皮は80年から200年生のヒノキの立木から採るが 200年生15本で一坪分しか採れない。年間4000坪分を必要とするが、それには、6万本のヒノキが必要。しかも一度皮を剥くと、8年から10年はその木からは採れない。とすると200年生のヒノキが60万本必要となる。また皮を剥く技術を持った元皮師(もとかわし)も少なくて日本で15~6人しかいない。今、ヒワダの供給量は、1000坪分くらいしかない。
材種も様々である。使う量は、そんなに多くはないが、同じ材料で同じ仕上げをしたいので質のいいものを探したくなり、入手に時間がかかる。特に松が不足している。
漆も、昨今は中国産が入ってきた。日本産は、質が良く持ちもいいが、5?6倍もの価格になるので売れなくなった。漆欠きの職人も減り、伝統的な漆を採る技術も失われてきた。
文化財を守るシステムとしての人の不足、資材の不足はまさに危機的状況である。
【平野秀樹 林野庁監査室長】(2003年4月から林野庁研究普及課長)
見渡す限りの木が何故売れないのか、の質問に対して、これまでの行政施策にとまどいがあるように思える。箱物が多すぎるのではないか。今、人の少ない島、山村等で聞き書きを実行しているが、本当に必要なのは、親身になって考えてくれる医師や弁護士や税理士などである。そういった処にも目を向けるべきと思う。
森林を4つのパターンに考えてみる。
1. 野生の森、屋久島や白神山のように世界遺産になるような森。
2. 家畜の森、今の人工林のような、木を使い回す為の森
3. ペットの森、里山や雑木林など、緑に渇望する人たちが会いに来るような森
4. アクセサリーの森、都市のビルの谷間の緑など
このうち、緑のペット化が著しい。そんな中で、木を使い回す、それも大径材としての材木に視点をおいているこの有識者会議の活動はとても意義深い。こうした活動がずっと続いて欲しいと期待している。
拡大造林の政策は、30年たって問題が山積してきた。お金や人手をかけないと成り立たない人工林施業、間伐するつもりの密植地が手入れされなかったり、あるいは、伐りっぱなしのままの山が増えている。過疎山村では境界すらわからなくなっている。結論として大切なことは、大径材にもっていくなど家畜の森を健全な状態にすることである。
85年前に全国の巨木調査が行われ、2年前にもフォロー調査が行われた。日本各地の巨木が消えた理由は、以前は落雷、台風だったが、最近は公共事業で伐られることが一番多い。
こうしたことに関心を持ち続ける社会を形成することが必要なのだろうと思う。
地域社会で林業経営が行われ、ふつうの人が暮らし続けることの出来る社会が求められている。
相続税に関しては、評価上の問題としてとらえている。資産の評価法については、積極的に改善していく手法が必要と思う。
もう一つ。仕事を楽しむきっかけとなる家づくりに関して。
職業に楽しみの要素があることは大事だ。例えば海女の世界には、アワビを採る楽しみが混じっていた。また女系社会のなごりを残すその社会は持続的な生産を可能にするため、ウェットスーツを着てはいけない、という決まりさえ残し続けていた。それによって自然管理がうまくなされていた。
こんなふうに、辺境コミュニティが機能することは、地域資源である地域材の活用にも役立つだろうと思う。これからの視点は、コミュニティの観点を含んだ小さな施策がそれぞれの地域で必要だということだ。
【野上 修 三峯神社禰宜 】
最近スギ花粉が問題になっているが、50年前に植えた木は、こんなに問題にならなかった。終戦後にうえた木の手入れ不足が問題なのだろうと思う。職務柄地鎮祭、棟上げなどで新築の建物を見てきたが、表面だけきれいな材が増えてきた。切り口をみると接着剤で張りあわせた集積材というのだそうだが、シックハウスやアトピー、喘息の問題など、将来的にもその化学反応など心配である。またほとんどが輸入材である。価格は安いのかも知れないが、地元の木で家を建てれば、山の手入れにも繋がるのにと今の、悪循環の社会を憂えている。
神社のまわりには、木を植える。神が降りてくるためにも必要なもの、神社と緑は切り離せない。100年1000年先を考えて大事にしていかなければならない。
【渡辺 隆 風基建設代表取締役 】
伝統木造はどうなるのか、に関して建築基準法の問題をあげる。
建築基準法では、建物を固い構造として考えなければならない。伝統的な木造軸組は柔な構造。構造計算が必要となる。しかし接合部の構造的データが無いので、そのデータベースつくりが急務な状態。構造計算自体も大変難しいものとなっている。
文化財の建造物は基準法の適用除外となっているが、(法3条)阪神淡路大震災以降構造補強が問題となっている。
最近、意見を表に出していこうとする動きがでてきた。構造の実大実験やデータづくり等も行われている。
また、木造軸組構法の技術的な問題を考えそれを継承していこうとする仲間が増えてきている。100年先の人の問題も考えて一昨年「日本伝統建築技術保存会」という組織ができた。文化財修理工事に関わる大工、工務店の全国でのはじめての集まり。正会員61社、準・賛助会員230社が参加している。技能の継承はもちろんのこと、工事の発注形式、入札制度など現場からの声を伝えたいと思う。また、木造軸組構法にこだわる90社の仲間の全国組織、木の家ネットワークもできた。
【内山 節 哲学者】
地域にある小さなお堂、地元の大工さんが直してきた。そういうものが消えていってしまうことに危機感があって、この有識者会議を共有しようと思った。木と人間の関係について考えていきたい。
上野村で巨木探しをやった事がある。巨木は山の神信仰と繋がっている。信仰と結びつきながら巨木が残されてきた。地域の神社に高齢木の天然ヒノキが2本あるが、かつては、10本近くあったらしい。それは、水道を引いたり、電灯線をひくための費用に当てられたという。私利私欲では切らない。神様との関係で皆の為に切るのは許される。
村に「山あがり」という言葉がある。博打や養蚕の相場で困った時には山へ上がれば1年くらいは暮らせるという。山上がりすると宣言すれば誰の山に入っても良い。村の人は味噌を持たせなければならない。味噌さえあればなんとかなる、それほど昔の山は豊かだった。森があれば何とでもなる。信仰と森との歴史が結びついて集落がある。長い歴史の中にそこに埋め込まれている信仰がある。
基盤となっていた地域の暮しがくずれてきて各地の神社仏閣も変質してきた。基礎にあった、人間と森との関係が崩れてきてただの文化財になってきた。お金を出して見るもの。そうならないために木と暮しの関係が大事だと思う。地域の小さな社に文化が残っている。
しかし村に大工がいなくなる。在来工法は工期がかかり、宿泊費を考えるとかえって東京より高くなる。山間地域であっても、住宅産業の大手工務店の家になる。
土台から壊れていく現実を何とかしていかないといけない。地域のお寺、お社、文化財というにはほど遠いものであっても地域の要としてきちっと守るようにしないといけないのだと思う。 建築物の維持だけでなく、無名の物を守るということでこの有識者会議に首を突っ込んでいる。既存の物をきちんと残していくことが大事と訴えたい。
●ここからディスカッション
平野: 五島列島や瀬戸内海にも「山あがり」によく似た文化がある。困窮島制度というもので、共有資源として磯資源・棚田・茅場・漁場などあるが、そこに行くと豊かになって戻って くる。
森林は50年で伐るとすると、伐った時は私有だが、49年数ヶ月は公益的機能の方が大きいいわば公的資源だというあいまいな存在。共有財産と私有財産の考えをもっと深く掘り下げなければいけないと思う。それには自治も含めた考え方がいるし、また共有財産としての巨木や大径材を守るだけではなく、伐ることに大きな意味があることを知らなければならない。共有財産を考えるという切り口からもこの運動は意味がある展開をすると思う。
内山: 上野村に共有林は無い。「山あがり」はどこの山に入っても良い。村における「総有」という考え方は誰かの所有物だけれど、皆のものでもあるという歴史的ルールが何となくある。今は、みんなのものという考えを含んだ私有という考え方が崩れてきている。
司会: 所有の線をもっとあいまいにしていく必要があるのか。
平野: 村有林でもない、私有林でもないそんなものを作れるのかについては、興味がある。
司会: 例えば物納して、みんなで総有というのは出来ないのか
平野: 契約関係とは違う結びつきがあるかという事だが、共通の夢は共通の利害が絡んでいないと描けない。サイバーコミュニティではだめだ。しかも、目にみえる範囲の人たちでないと共通の夢は描けないのではないか。そのシステムは工夫しないといけないのだろう。
内山: 何とか林業で頑張ろうという人たちはいても、この数年の木材価格では、動きようがない。管理できて成り立っているのが10%,保護林が10%, あとはあいまいなまま失敗している。あいまいな物に対して、低コストで針葉樹も混ぜていくという手法が開発されていない。
司会: 自分の地域の中で、なにかできないかと思うのだが。
内山: なぜ、輸入木材がいけないのか説明できない。なぜ文化財の建物を、日本の古来の材を使わないといけないのか。文化の問題として日本の木造建築や歴史を考え、文化論で議論して欲しいと思っている。
司会: なぜ、文化財修復が元と同じ木でないといけないのか。
近藤: 文化財補修はオリジナルにこだわっている。(同樹種、同品質、同技術) 必ずしも良質のヒノキにこだわっているわけではない。民家にはそれなりのふしくれた材を使う。復原にこだわる。調査をしたうえで、歴史的な変遷を押さえて経緯をはっきりさせたうえでいつの時代の姿にするか検討して修理をする。結果として当初の形になることが多い。
司会: 建物には時間が組み込まれている。家を作るのにもうひとつの物語が必要。
近藤: ヨーロッパは、改修されたものを残そうという考え方が強い。日本は途中に改造された形に残すには無理がある場合が多い。保存上に影響があるので、当初のシンプルな形で残すほうが無理がない場合が多い。
渡辺: 住宅20年評価があった。しかし50~80年生の木を使うので、最低そのくらい持つようにしたい。使い手の意識変わってきた。長く住み続けたいと思う人が増えつつある。伝統工法がそれに繋がる。
司会: 伝統木造で作るのは難しいが、国の取組も変りつつある。
国土交通省木造住宅室長:
・伝統工法の品質・工法をしっかり検証する。文化的価値、地域の伝統などについても情緒的ではなく、とりいれたい。構造的に強いなら環境や防火についても研究者の知恵や作り手の想いを結集する必要がある。
・作り手の技術の継承。後継技能者の育成にも取り組みたい。
この後、夕食をはさみ、それぞれの分科会に移動し熱心な議論が続けられた。
1,文化財と補修用材に関する分科会(伊藤・近藤)
2,伝統建築に関する分科会(渡辺・野上)
3,宗教・哲学に関する分科会(内山)
翌9日は、三峯神社本殿での早朝勤行。扉を開け放った拝殿、凍りつくほどの冷気の中での参拝は貴重な体験となった。ドドンと腹に響く太鼓の振動も忘れられないだろう。雪に足をとられながら三峯神社境内の散策の後、解散。午後から希望者は東大秩父演習林見学に参加した。