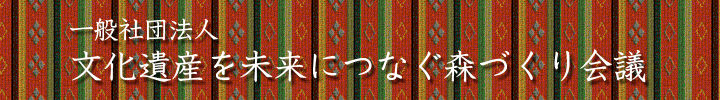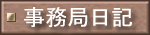« NO.405 「京都五山 禅の文化展」 | メイン | NO.407 「セロトニン」が大事って »
2007年09月01日
NO.406 コロタイプ雑感ーゼラチン
以前、便利堂のコロタイプ印刷に関して、コロタイプというのは、「感光液を含んだゼラチンは光の量に比例して硬化する」という性質を利用したもの、と書きましたが、この『ゼラチン』が気になって調べてみました。
コーヒーゼリーを作る時に溶かして混ぜるあのゼラチン?というイメージしかなかったものですから、自分としてはすこぶる奇異な印象を受けたのですよ。
でもゼラチンについて調べてみてビックリ。
ゼラチンを基材とする乳剤が作られた19世紀末から現代まで、ゼラチンは写真産業と共に歩み、輝かしい発展を支えてきた、というのです。
ゼラチンを溶かし、臭化カリウムの溶液を加え、暗室内で硝酸銀の溶液を加えて攪拌すると、乳白色の液が出来て、これを、フィルムベースやバライタ紙に塗布して乾燥させると、感光膜になり、写真フィルムや印画紙になるんですって!!
(日本ゼラチン工業組合HPより)
じゃぁ「ゼラチン」って何?
三省堂の新国語中辞典によると、単純たんぱくの一種。動物の骨・皮膚・腱などを水と長く煮た液から取り出し、白粉または透明な薄片として得られる。熱湯には容易に溶け、冷却すれば固まる。食用のほか止血剤、細菌類の培養基、写真感光膜などに使う。不純なものはにかわとして接着剤にする。
ついでに、「にかわ」は、
(煮皮の意)膠 獣・魚類の骨や皮・腱・腸などを煮た液をかわかして固めたもの。接着剤に使う。精製した白色のものをゼラチンという。
何が言いたいのかって、もうお分かりでしょうか。
日本画を描くときは、湯煎器でにかわを溶かし、それで顔料を混ぜて色を作りますし、墨だって、油煙や松煙をにかわで練り固めたもの。
コロタイプの印刷にも、写真のフィルムにも、絵の具や墨、美しい音を奏でるバイオリンの接着剤にだって、ゼラチンやにかわが使われているのですよ。
つまり、若冲の描いた「動植綵絵」も、「京都五山 禅の文化展」でみた数々の墨蹟も、たくさんの「命」と引き換えに生み出されたものだったのです。
食べ物だけじゃなく、その他にも数えられない程の「命」が使われてきたということ。
知らなかった、というよりも今まで気がつかなかった、考えもしなかった、そんな自分のうかつさに愕然としたのです。
(あし)